本ページはプロモーションが含まれています。
こんにちは、りりぃです!
妊娠中や産後には、ママとパパを助けてくれる助成金や給付金の制度がありますが「どんな制度があるかよく分からない…」という方も多いと思います。
そんな制度知らなかった…
申請を忘れていてもらえなかった…
ということにならないように事前に確認しておくことが重要です。
今回は制度をまとめてみましたのでスムーズに手続きができるように参考にしてください!
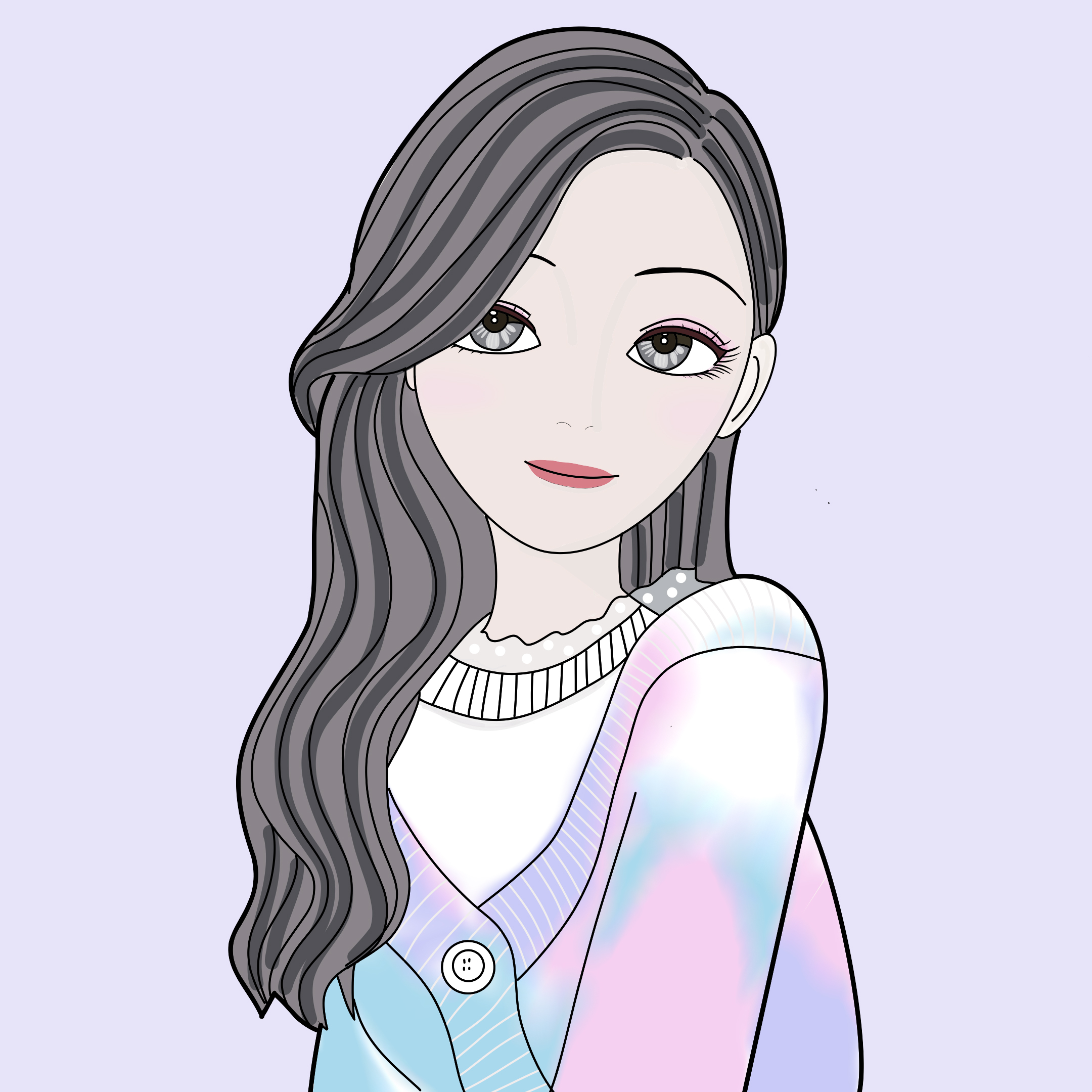
この記事は以下のような方におすすめです☆
- 妊娠中の方・出産を控えている方
- 産後のママ・パパ
- これから子どもを持つ予定の方
もらえるお金一覧
妊娠・出産のタイミングでは、国や自治体、勤務先の制度などからさまざまな給付金や助成金を受け取ることができます。
妊娠中は体調の変化も大きく、出産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなるため、事前にどんな制度があるかを把握しておくことがとても重要です。
また、給付金や助成制度の対象となるかどうかは、ママの勤務状況や雇用保険の加入有無、健康保険の種類(社会保険か国民健康保険か)によって異なります。
パパが被保険者の場合、ママが扶養に入っているか、自営業か、パート勤務かどうかによっても大きく変わってきます。
制度としては以下のものがあります。
全員がもらえるお金
- 妊婦検診費の助成
- 出産育児一時金
- 児童手当
- 乳幼児医療費助成
- 医療費控除 ※確定申告が必要
- 高額療養費
ママの状況によりもらえるお金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 傷病手当金
- 退職者の所得税還付申告 ※確定申告が必要
- 失業給付受給期間の延長
何が対象になる?早見表でチェック!
さまざまな制度が実際に自分がどの制度が対象なのかよくわからないと思います。
そこでご自身の状況に応じて「何が対象になるのか」「どれが条件つきか」をひと目で確認できる早見表を作成しました。
この一覧を見ながら、自分に該当するものを一つずつチェックしてみてください。
わかりづらい制度もありますが、後半では一つひとつの制度についても詳しく解説していますので、必要に応じて各項目のリンクからご覧ください。
早見表の○が対象、×が対象外、△が条件によっては対象となります。
| 妊婦検診費 の助成 |
出産育児 一時金 |
児童手当 | 乳幼児の 医療費助成 |
医療費控除 | 高額療養費 | 出産手当金 | 育児休業 給付金 |
傷病手当金 | 退職者の 所得税 還付申告 |
失業給付 受給期間の 延長 |
|||
| 社会保険 | ママ本人 が加入 |
仕事を続ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 仕事を辞める | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ||
| パパの 社会保険 に加入 (被扶養者) |
パート等を続ける (雇用保険あり) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| パート等を辞める (雇用保険あり) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ||
| 専業主婦・自営業・ パート等 (雇用保険なし) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ||
| 国民健康保険 | パート等を続ける (雇用保険あり) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| パート等を辞める (雇用保険あり) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ||
| 専業主婦・自営業 ・パート等 (雇用保険なし) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ||
各制度の内容
ご自身の対象の制度は確認できたでしょうか?
それでは、それぞれ各制度の内容を確認しましょう。
詳細は別記事で説明していますので、それぞれの記事をご参考ください。
妊婦検診費の助成
妊娠が確定した人が妊婦検診にあたり、妊婦検診14回程度分の費用を助成してくれる制度です。
妊婦検診の回数は14回程度とされているため、原則は14回分の助成が基本になっていますが、無料で受けられる検査項目や上限額は自治体によって異なります。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
出産育児一時金
健康保険に加入していれば、入院・分娩費として健康保険から基本50万円がもらえる制度です。
双子の場合は100万円となります。
健康保険組合や自治体によっては、さらにプラスでもらえる場合もあります。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
児童手当
子どものいる家庭で、子どもが高校3年生になるまでの間、毎月給付金がもらえる制度です。
3歳未満は月1万5000円、3歳から高校3年生までは月1万となり、総額が約200万が給付されます。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
乳幼児医療費助成
病院にかかることの多い赤ちゃんの医療費を、自治体が全額、または一部を助成してくれる制度です。
助成対象となる子どもの年齢は自治体によってさまざまですが、基本的に中学卒業までの間は助成されます。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
医療費控除
1年間で家族全員の医療費の合計が10万円を超えた場合に、確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくる制度です。
戻ってくるのは所得税ですが、申告をすると翌年の住民税も下がる可能性が高いです。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
高額療養費
同じ医療機関で支払った1か月間の保険適用医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額分が助成される制度です。
妊娠・出産でかかる医療費は基本健康保険は適用ではありませんが、切迫流産・早産や帝王切開など、健康保険の適用になる場合があります。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
出産手当金
産休に入るママに対して、健康保険から産休の日数分の手当金が給付される制度です。
期間は出産前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から、出産日の翌日以降56日目までで、日給の3分の2×産休の日数分をもらうことができます。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
育児休業給付金
育休中のママ・パパに対して、雇用保険から育休期間中に給付金がもらえる制度です。
期間は原則子どもが1歳になるまでで、育休開始から180日間は「日給×0.67×育休期間」、181日目以降は「日給×0.5×育休期間」になります。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
傷病手当金
妊娠・出産時のトラブルに限らず、勤め先を病気やケガで、連続して3日を超えて休むと、4日目から手当金が給付される制度です。
支給が始まった日から最大1年6ヵ月間もらうことができます。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
退職者の所得税還付申告
妊娠・出産のために年度の途中で退職した場合に、年末調整を受けられていないため、翌年に確定申告をすると払いすぎた所得税が戻ってくる制度です。
また、申告をすると翌年度の住民税が下がる可能性もあります。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
失業給付受給期間の延長
妊娠・出産のために退職したママが、産後に再就職を希望している場合に、失業給付の受給期間を延長できる制度です。
失業給付は通常、退職日の1年以内に受給をし終えなければならないところ、最長で4年まで延長することができます。
\詳細は下記の記事をご覧ください/
まとめ
今回の記事では、妊娠・出産でもらえるお金について説明しました。
ご自身がどの制度が利用できるか確認できましたか?
まずは、どんな制度があって、どの制度が利用できるのかを確認しておき、後から「もらえてない!」とならないようにしましょう。
妊娠・出産は何かとお金がかかりますので、しっかりとお金をもらい、今後の生活の助けや、子どものための貯蓄として準備ができるといいですね。
今回ご紹介した「医療費控除」「退職者の所得税還付申告」は確定申告が必要になります。
確定申告と聞いても
「何を準備すればいいの?」
「計算がややこしそう…」
と思う方も多いと思います。
そんな方にはマネーフォワード クラウド確定申告をご活用ください!
マネーフォワード クラウド確定申告は、ステップに沿って入力していくだけで
確定申告に必要な書類をカンタンに作成できるサービスでのため、確定申告が初めての方でもカンタンにできちゃいます♪
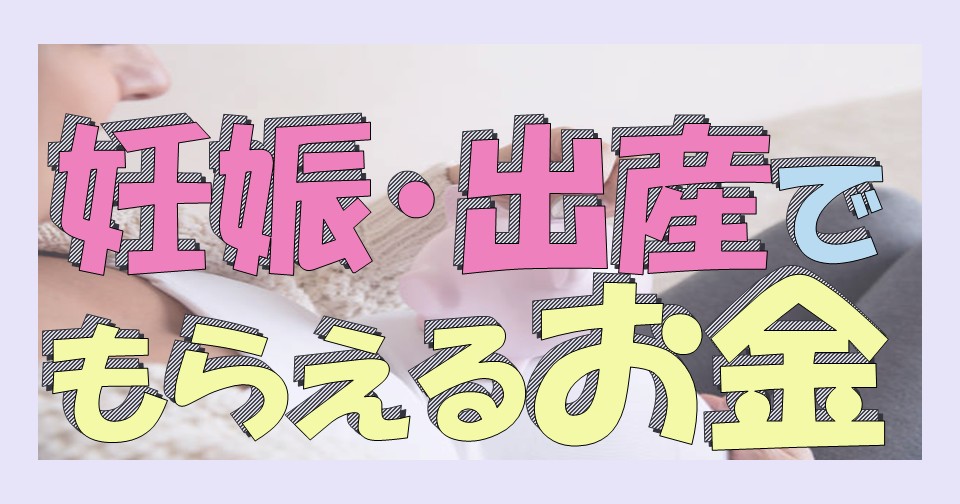
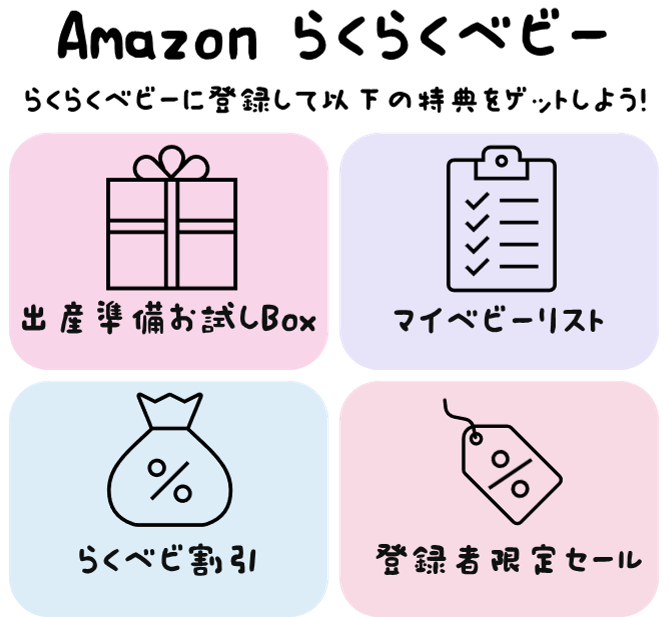




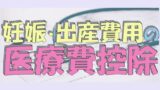


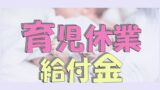
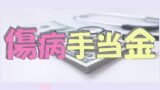



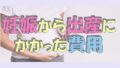

コメント