本ページはプロモーションが含まれています。
こんにちは、りりぃです!
産休中は給料が出ない会社がほとんどのため、その間の生活をサポートするために、加入している健康保険から「出産手当金」として手当金が支給されます。
ただ、加入している健康保険によっては、もらえない場合もあるので、まずは勤め先に受給資格の確認が大切です。
今回はこの出産手当金について説明します。
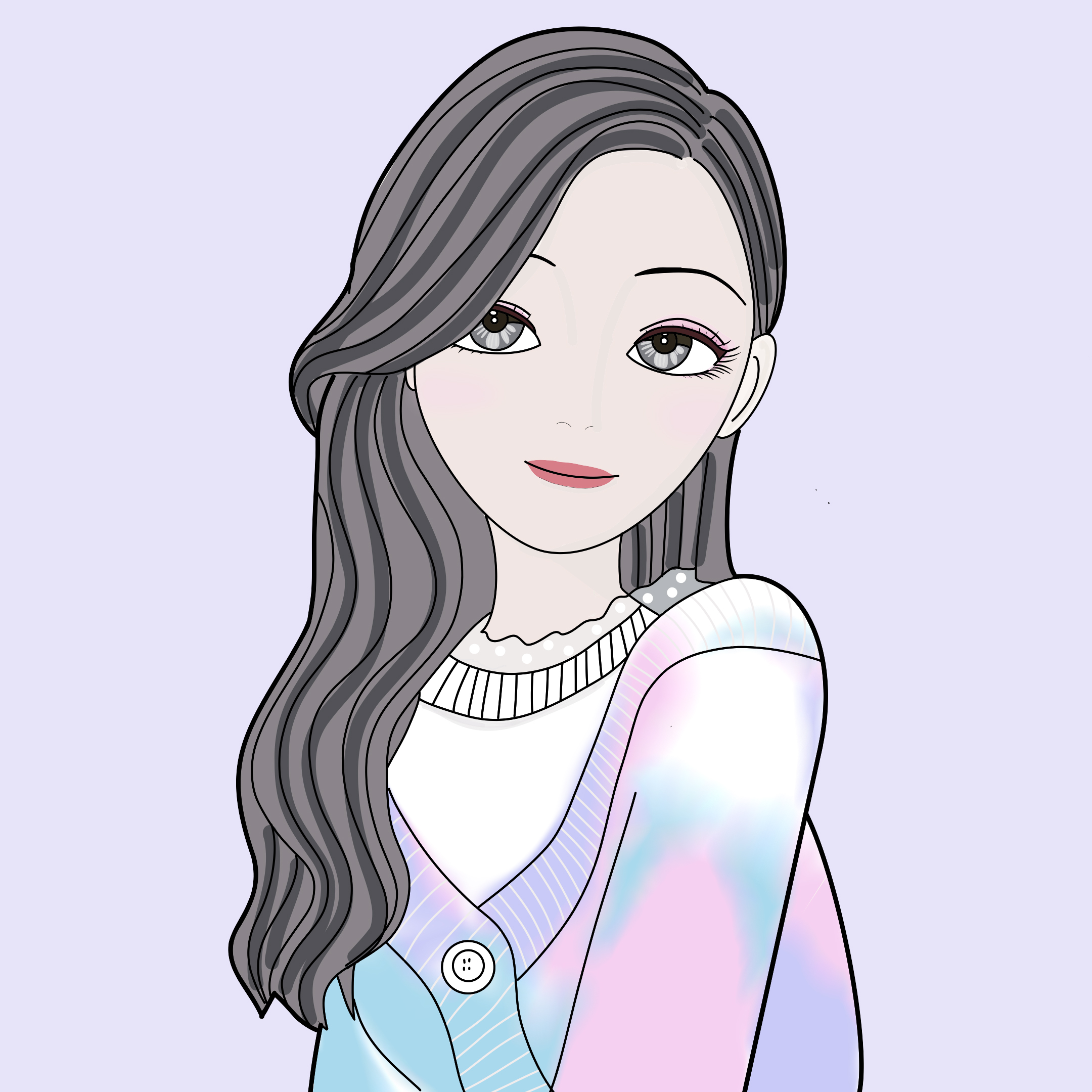
出産手当金は産休に入ってすぐにもらえるわけではありません。そのため、産休に入ってすぐの生活に困らないように貯蓄をしておきましょう♪
出産手当金とは?対象者・支給条件・注意点をわかりやすく解説
まずは、出産手当金の概要を確認しましょう。
対象者
対象者は、勤め先の健康保険に加入していて、産後も仕事を続ける人になります。
もらえる金額
手当金は、日給の3分の2×産休の日数分となります。
産休の日数は出産日以前42日(双子以上の場合98日)から出産後56日までの間で、仕事を休み、給料がもらえない日になります。
実際に休業した日や、出産日が出産予定日の前かあとかで、産休日数は変わります。
そのため、産休日数が変わるのに伴い、もらえる金額も変わります。
申請時期
申請時期は、産休明けの産後56日経過後になります。
産休の途中で提出することが可能な場合もあります。
受け取り時期
受け取り時期は、申請から約2週間~2ヵ月後になります。
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは以下の通りです。事前に確認しておきましょう。
- 健康保険出産手当金支給申請書
(産休前に入手した用紙に、産院と勤め先で必要事項を記入してもらいます。)
出産手当金の手続きの流れを時系列で解説
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
①妊娠中
まずは勤め先で受給資格があるかを確認しておきます。
② 産休前
勤め先などで「健康保険出産手当金支給申請書」の用紙をもらいます。
③ お産入院時
必要事項を記入して、お産入院時に忘れずに持っていきます。
④ 入院中
産院で申請書にある出産証明書欄への記入をお願いし、必要事項を記入してもらいます。
⑤ 産休終了後もしくは産休中
申請書を勤め先へ送り、必要事項の記入と健康保険への提出の依頼をします。
自分で直接、健康保険へ提出する場合もあります。
⑥ 申請後
申請から約2週間~2ヵ月後に指定の口座にお金が振り込まれます。
出産手当金でもらえないケースとは?注意点・落とし穴を解説
事前にこれだけは知っておいてほしい注意点を紹介します。
国民健康保険組合だともらえるケースがある
産後も仕事を続ける場合でも、国民健康保険の場合は、「出産手当金」はもらえません。
ただし、国民健康保険組合では、建設国保など一部の組合は支給しているので、ご自身が加入している国民健康保険組合に確認してみましょう。
会社から給与ができるともらえない
産休中に給料の3分の2以上が出る場合は、「出産手当金」はもらえません。
給料の3分の2未満が支給される場合は、給料の3分の2との差額分が健康保険から支給されます。
産休中の給料支給については、勤め先に確認しておきましょう。
公務員や契約社員の場合
公務員
公務員の場合は、共済組合から「出産手当金」がもらえます。
手続きは、一般的な健康保険組合の場合とほとんど同じなので、詳しくは共済組合の窓口で確認してみましょう。
契約社員
契約社員の場合は、勤め先の健康保険に加入し、産休を取得できれば「出産手当金」がもらえます。
ただし、派遣会社を通した契約の場合は、条件を満たしているかどうか派遣元の会社に確認をしましょう。
【体験談】出産手当金はいつ振り込まれた?
私が実際に出産手当金をもらえたのは産休期間が終了してから1か月後でした。
そのため、産休後にすぐにはもらえないことを認識しておき、数か月分の生活費の貯蓄をしておくことが大切です。
また、健康保険に提出する「健康保険出産手当金支給申請書」は産院にも必要事項記入してもらうのですが、私の産院では記入してもらうための事務手数料として3300円かかりました。
産院よって費用は異なると思いますが、事務手数料が必要になる場合があることも認識しておくと安心です。
まとめ:出産手当金を確実にもらうために知っておくべきポイント
出産手当金は、産休中の収入がなくなる時期をサポートしてくれる大切な制度です。
ただし、「誰でももらえるわけではない」「すぐに支給されるわけではない」という点に注意が必要です。
特に以下の点を押さえておきましょう。
- 出産手当金の対象となるのは、健康保険に加入し、産後も働く予定の人
- 支給額は日給の3分の2×産休日数(給料が出ていない日)
- 申請は原則、産後56日経過後。受け取りまでは2週間~2ヵ月程度かかる
- 産院での書類記入に事務手数料がかかるケースもある
- 国民健康保険では原則もらえないが、組合によっては支給されることも
- 給料が出ると支給されないケースもあるため、事前に会社に確認を
出産に関する公的制度は手続きや条件が複雑なものもありますが、事前に確認・準備しておくことで安心して産休を迎えられます。
しっかり制度を活用して、安心して出産・育児に臨みましょうね♪

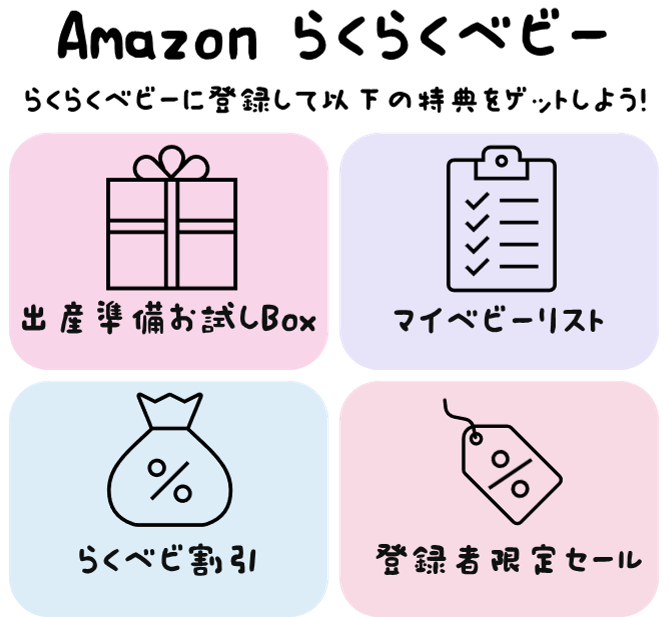
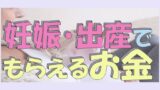

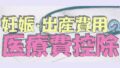


コメント