本ページはプロモーションが含まれています。
こんにちは、りりぃです!
育休期間中は原則、無給となります。
そこで育休後も仕事を継続するママとパパを対象に、休業中の家計を支えてくれるのが、育児休業給付金です。
雇用保険に加入していて、諸条件を満たしている人が対象で、パート等の場合も対象となりますので説明します。
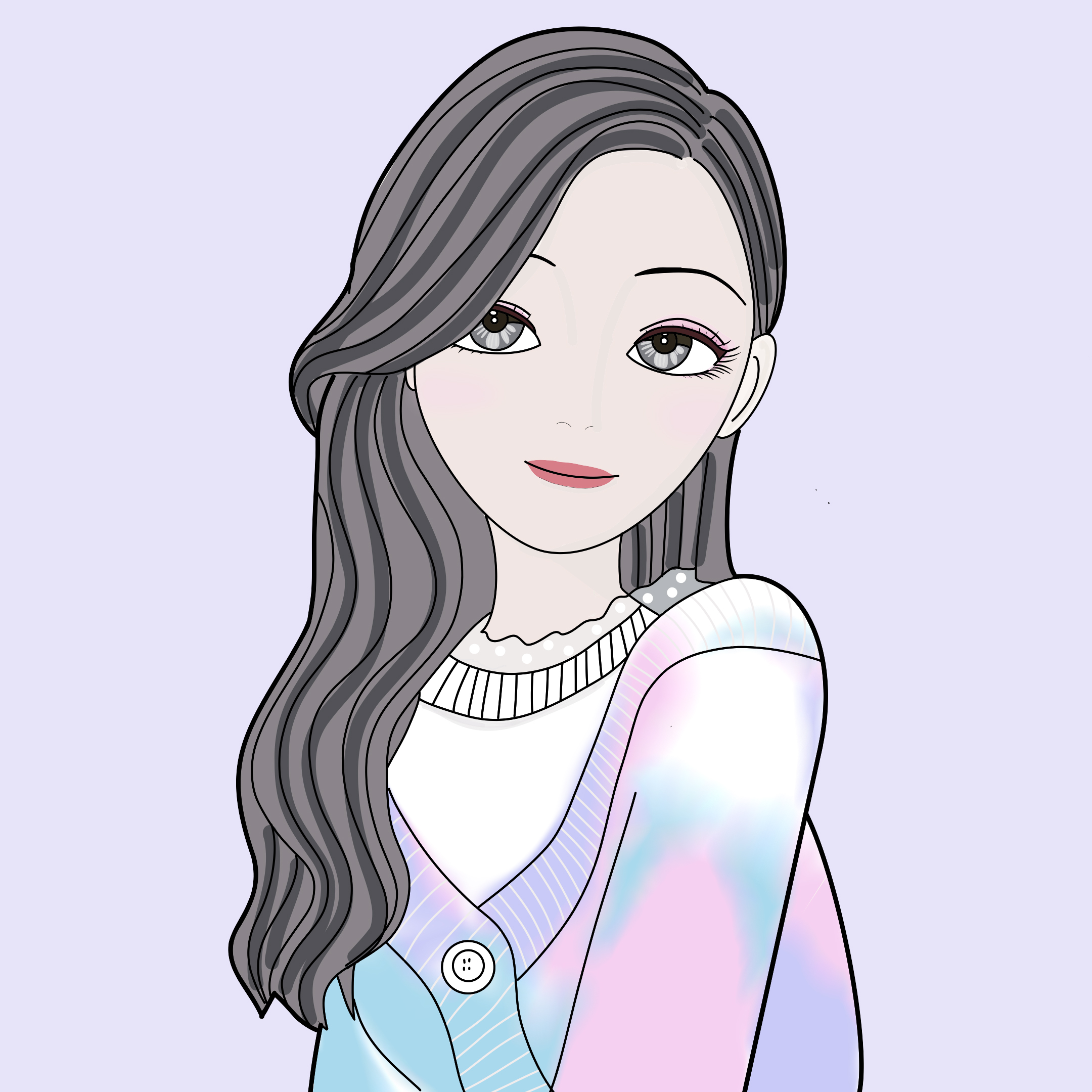
2025年4月から、夫婦で育休を取得する場合に、給付金が上乗せされる「出生後休業支援給付」がスタートします。夫婦で育休取得を考えている場合は、併せて確認しましょう♪
育児休業給付金とは?もらえる条件や対象者をわかりやすく解説
まずは、育児休業給付金の概要を確認しましょう。
対象者
対象者は、雇用保険に加入していて、育児休業をとり、職場復帰する人になります。
雇用保険に加入していても条件をクリアしないともらえないので、勤め先に確認をしましょう。
もらえる金額
もらえる金額は、休んでいる期間によって異なり、下記の通りになります。
・育休の最初の180日間
日給 × 0.67 × 育休として休んだ期間
・181日目以降
日給 × 0.5 × 育休として休んだ期間
申請時期
申請時期は、勤め先に申請する場合は、産後の育休に入る前になります。
受け取り時期
受け取り時期は、初回は育休開始から約2~5か月後となります。
その後は、約2ヵ月ごとになります。
初回の受け取りは育休開始からかなりの時間を要する場合がありますので、育休に入ってからすぐにもらえないということを注意しましょう。
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは以下の通りです。
勤め先で用意をしてもらえるものもあるので、事前に確認しておきましょう。
- 雇用保険 被保険者 休業開始時 賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 雇用契約書など
- 出勤簿
- 賃金台帳
- 母子健康手帳のコピー
- 申請者のマイナンバーがわかるものなど
育児休業給付金の申請手続きの流れを時系列で解説
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
①妊娠中
まずは勤め先に育休が取れるかを相談し、給付金がもらえるかを確認します。
② 産休前
勤め先で「育児休業給付金」申請の必要書類をもらいます。
振込口座にする金融機関などを記入する書類なので、大切に保管しておきましょう。
③ 産後
書類に必要事項を記入します。
④ 育休に入る前
必要書類を勤め先に提出します。
ご自身でハローワークへ提出する場合もありますので確認しておきましょう。
⑤ 育休中
育休開始から約2~5か月後、「育児休業給付金」の初回振り込みがされます。
初回以降は、約2ヵ月ごとに振り込みがされます。
初回以降の手続きは、勤め先がやってくれるのが一般的ですが事前に確認しておきましょう。
育児休業給付金がもらえないケースとは?
育児休業給付金がもらえるのは、以下の4つの条件をすべて満たしている人になります。
契約社員やパート、アルバイトも雇用保険に加入していて以下の条件を満たせばもらえます。
- 雇用保険(または共済組合)に加入していて育児休業をとり、その後も働き続ける人
- 育児休業中、休業開始日前の給料に比べ、8割以上の給料が出ない人
- 育児休業をとり、育児休業開始から1ヵ月ごとの区切りに休業日が20日以上ある人
- 育児休業開始日を起算点として、その前2年間に、原則1ヵ月に11日以上働いた、または、労働時間が80時間以上ある月が通算12か月以上ある人
ただし、雇用保険に加入していても、育休を取らない人、妊娠中に勤め先を退職する人、産休後に退職する予定の人、育休中に給料が8割以上出る人はもらえません。
まとめ:育児休業給付金をしっかり活用して安心の育休ライフを
育児休業給付金は、育休中の経済的不安を軽減してくれる心強い制度です。
ただし、受給にはいくつかの条件や申請手続きが必要であり、申請時期や必要書類についても事前の準備が欠かせません。
特に、初回の給付までに時間がかかることを想定して、早めの資金準備をしておくことが大切です。
また、2025年4月からは「出生後休業支援給付」もスタートし、夫婦で育休を取得することで給付額が上乗せされる仕組みも始まります。
共働き家庭にとっては大きなメリットになりますので、ぜひ併せて検討してみてくださいね。
育休中も安心して子育てに専念するために、制度を正しく理解し、賢く活用していきましょう。

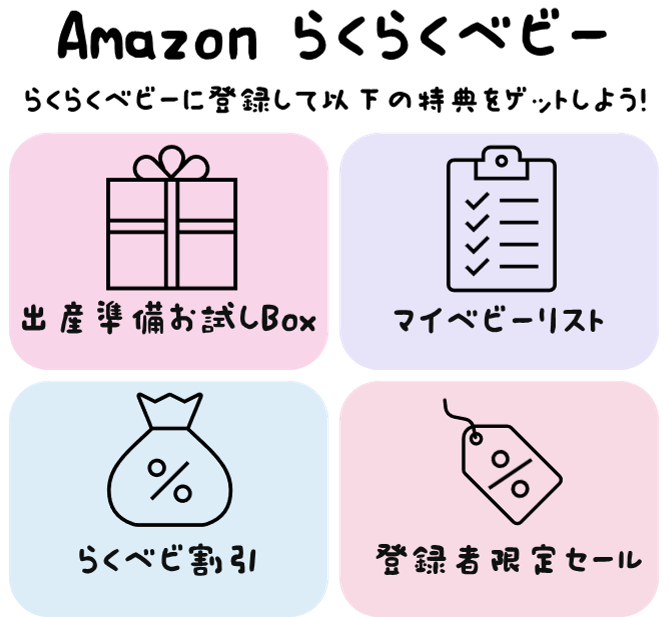
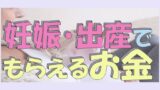



コメント