住宅は賃貸か持ち家どちらがいいか?というのは永遠のテーマになっています。両方ともにメリット・デメリットがあるのでどちらがいいかはそのご家庭でそれぞれで判断いただくのがいいと思います。今回は、持ち家が欲しいと考えている場合の住宅ローンについて紹介します。
いざ、持ち家を購入しようと思っても、住宅ローンがいくら借りれられるかによって、購入できる家も変わってきますので、いくら借りられて、いくらなら返せるか確認して、購入物件の検討をしましょう!
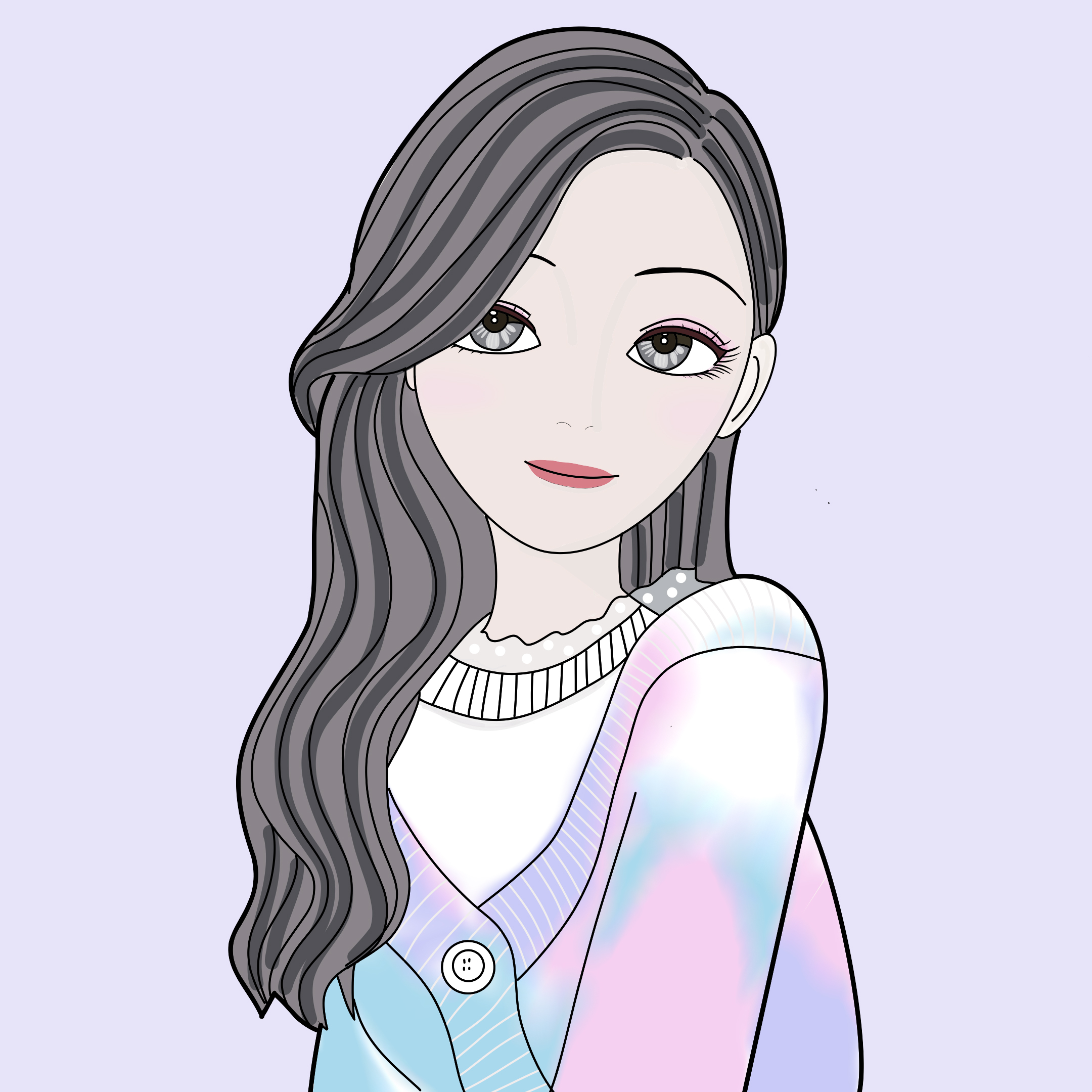
賃貸か持ち家かどちらがいいとは一概に言えませんが、持ち家はやっぱり憧れがありますよね♪
購入する場合は、返済計画もしっかり立てて、住宅ローン破綻といったことにならないようにしましょう!
住宅ローンの借り入れ可能額ってどうやって決まる?
住宅ローンは、希望する金額をいくらでも借りられるわけではなく、契約する本人がどれだけ借りられるかを示す「借入可能額」があります。その金額は一律で決められるものではなく、複数の要素によって判断されますが、明確な基準は公表されていません。主には以下のような基準を基に、金融機関による審査のうえで決定されます。
年収
契約する本人が安定的にローンをしっかり返済する能力があるかどうかを判断するために、現在どのような会社で、何年勤務していて、いくら年収があるのかということを示す必要があります。
公務員など安定性のある職業だったり、年収が多かったりすると、借入希望額での住宅ローン審査を有利に運べます。また、自営業や正社員でもインセンティブ契約の場合、収入が多くても安定性を欠くために減額されるケースもあります。勤め先が官公庁や上場企業の場合、借入金額だけでなく金利も優遇されます。
返済負担率
次に住宅ローン審査で重視されるのが、返済負担率です。返済負担率とは、年収に占める住宅ローンの年間の返済額の割合を指します。借入希望額がこの返済負担率を超えると、返済負担が大きいと判断されて減額されたり、審査から落とされたりします。なお、ここでの年収は手取りではなく額面です。
返済負担率の基準は金融機関や借り入れる人の年収などによって変わりますが、およそ20〜40%以内に定められています。ただ一般的には25%以内程度に押さえておくほうが安心だといわれています。
融資率
融資率とは、購入する住宅価格に対する住宅ローンの借入金の割合のことを指します。簡単に言い換えると、物件価格に対して、借り入れで賄う部分の割合のことです。融資率が高ければ、建設・購入費に対する借入額が大きくなるので、自己資金が少ないことを意味します。
融資率は下記の通り計算され、住宅ローンの審査では、物件に対する融資率が高くなるほど適用金利が上がるケースが多いです。
借り入れ金額÷物件購入金額×100%
融資率の上限は、住宅ローン商品ごとに異なり、最近は融資率が100%の金融機関が多くなっています。また、物件購入額に住宅ローンの事務取扱手数料や登記関連費用などの諸費用も含めた金額を貸し出している金融機関もあります。
担保価値
物件の担保価値、いわゆる資産性も借入可能額を決める条件の一つとなり、支払いが滞った際に、しっかりと回収できるかどうか、物件を事前に確認します。
住宅ローンを借りる際には、金融機関が物件に「抵当権」を設定します。住宅ローンの返済が滞った場合でも、抵当権があれば、金融機関は物件を競売にかけて返済に充てることができます。
物件に抵当権を設定することを「担保にする」といい、担保にする物件の価値、すなわち資産性は借入限度額に影響することになります。
年収別 返済可能額一覧表
借入限度額はあくまでもひとつの目安であり、無理なく返済を続けていける金額を示しているわけではありません。そのため、もし返済が滞ってしまえば、遅延損害金として利息が発生したり、最悪のケースでは住宅が差し押さえられてしまったりすることもあります。
住宅ローンを組む際には、安定して返済を続けられる「返済可能額」を考慮しておくことが何よりも大切になります。
返済負担率は25%程度に押さえておくのが安心といわれていますので、年収別の返済負担率25%時の返済可能額を一覧にしましたのでご確認ください。なお。金利は固定金利1.5%としています。
|
年収 |
毎月返済額 |
借入可能額 |
借入可能額 |
|---|---|---|---|
|
300万円 |
6.3万円 |
1,575万円 |
2,058万円 |
|
400万円 |
8.3万円 |
2,075万円 |
2,711万円 |
|
500万円 |
10.4万円 |
2,600万円 |
3,397万円 |
|
600万円 |
12.5万円 |
3,125万円 |
4,083万円 |
|
700万円 |
14.6万円 |
3,651万円 |
4,768万円 |
|
800万円 |
16.7万円 |
4,176万円 |
5,454万円 |
|
900万円 |
18.8万円 |
4,701万円 |
6,140万円 |
|
1,000万円 |
20.8万円 |
5,201万円 |
6,793万円 |
返済負担率を25%に設定した場合、25年ローンでは年収のおよそ5倍、35年ローンでは年収の6~7倍がひとつの目安だといえます。
住宅ローンを借り上での注意点
固定資産税やメンテナンス費用がかかる
住宅を購入すると住宅ローンとは別に固定資産税がかかります。
固定資産税とは、土地など不動産を所有していると発生する税金で、自治体が決めた固定資産税評価額を基準に算出されます。また、土地の評価は一定ではなく変動します。土地の評価が上がれば、支払う税額も高くなる可能性があるので注意が必要です。
また、マンションに住む場合は、管理費や修繕積立金が毎月かかります。管理費とは、マンションの安全と美化を維持するためにかかる費用のことで、修繕積立金は、老朽化にともなう工事費のために積み立てるお金です。
戸建て住宅では管理費や修繕積立金は必要ありませんが、建物の経年劣化、家の中のインフラ設備の改修や修繕などが発生しメンテンナンスをする必要が出てきます。
購入時には諸経費がかかる
住宅ローンを組む場合は、住宅ローンとは別に諸経費として費用が発生します。諸経費とは、以下のような税金や手数料のことで、必要となる費用は、どの金融機関を利用するか、どのような物件を購入するかによっても大きく変わります。
目安としては、借入額に対し新築物件だと3~7%、中古住宅の場合は6~10%といわれています。さらに、条件によっては数百万円が必要となる場合もあります。
金額の違いはありますが、住宅ローンを組む際の諸費用は必ず発生します。
購入を検討している住宅価格のみならず、諸費用を含めた上で購入予算を考えましょう。
・融資手数料
・ローン保証料
・団体信用生命保険料
・仲介手数料
・印紙税
ボーナス払いはしないほうがいい
ボーナス払いとは、ボーナスが支払われる月だけ毎月の返済額とは別で住宅ローンの金額を支払うものです。このボーナス払いはできれば利用しないほうが賢明です。
ボーナス払いを併用すると、月々の返済額は軽減されるというメリットはありますが、元金の減りが遅くなるため毎月の利息負担額を考えると総返済額は多くなってしまいます。
また、転職や業績悪化などでボーナスの支給月が変更されたり、減ってしまったり、支給自体がなくなったとしても、ボーナス払いはその時の事情は考慮されず、年2回のボーナス払い分の引き落としが発生してしまいます。そのため、ボーナス払いを併用することはあまりおすすめしません。
まとめ
今回は、住宅ローンの借入限度額、年収別の返済可能額、注意点を説明しました。
住宅ローンを借りるにあたって一番大事なことは「借入限度額は、返済可能額とは異なる」ということです。借りられたからと言って返済できるとは限りませんので、できるだけ返済負担率は25%程度に押さえたいところですね。
住宅ローンを借りるにはそれ以外の費用がかかることも把握しておかなければなりません。住宅ローン以外の出費が払えない…とならないようにも事前に確認しておくことが大切です。
無理のない返済プランで、夢のマイホームが購入できるといいですね!
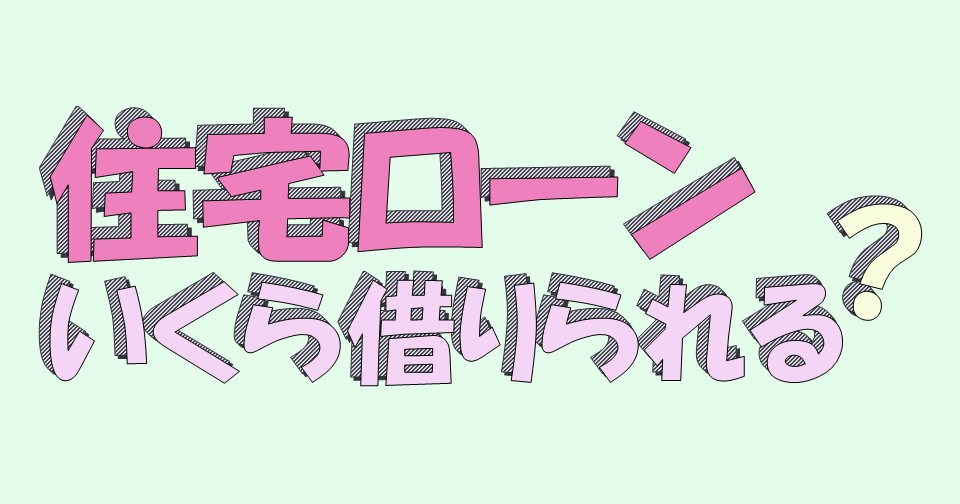



コメント