本ページはプロモーションが含まれています。
こんにちは、りりぃです!
赤ちゃんは何かと病院にかかることが多く、その医療費も回数が多い分高額になります。
そのため、自治体が赤ちゃんの医療費を全額、または一部を助成する制度「乳幼児の医療費助成制度」があります。
いくらで、何歳まで、などの助成内容や対象年連は自治体によって異なりますが、助成範囲を拡大する傾向にありますので説明します。
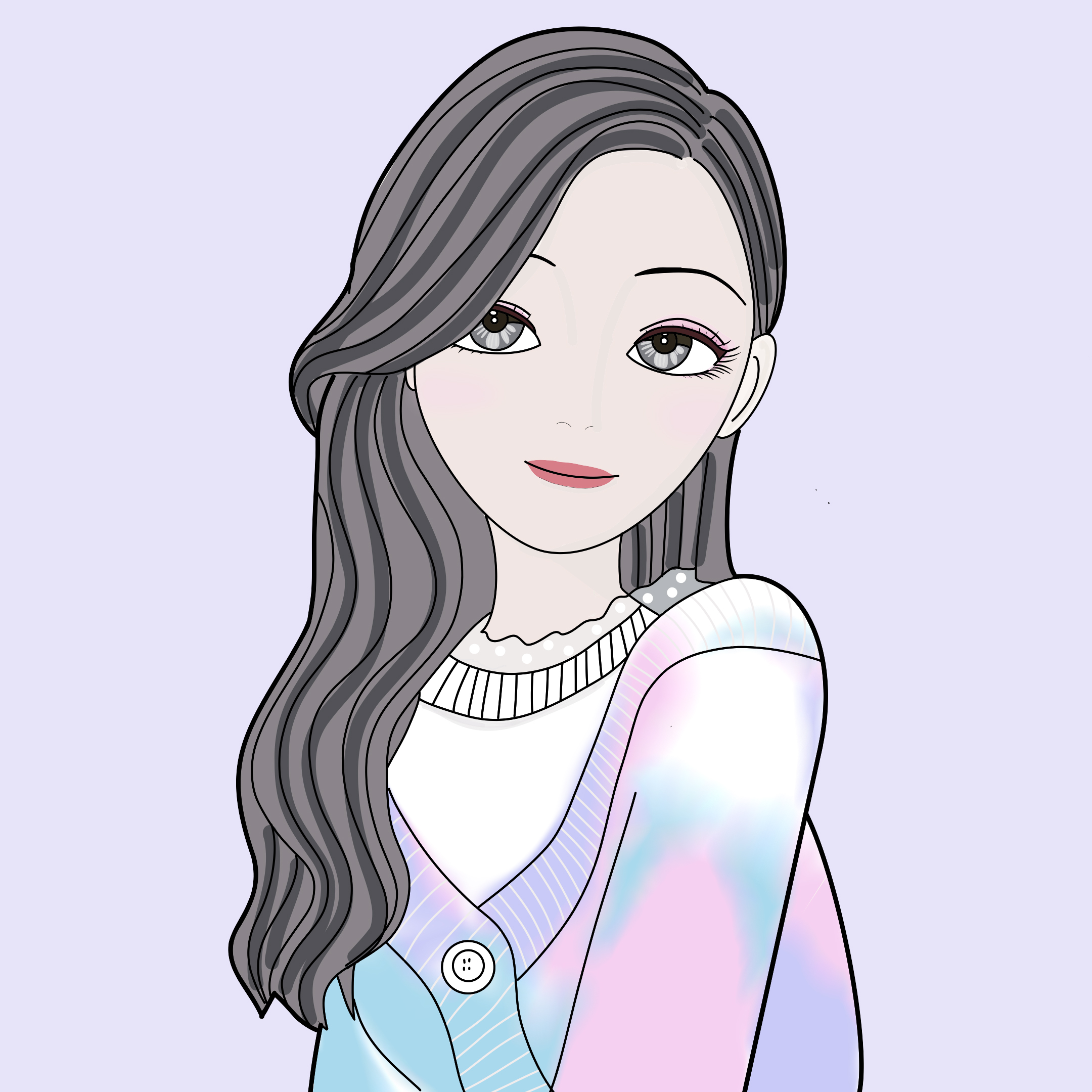
助成内容は自治体によって異なるため、まずはお住まいの自治体のウェブサイトなどで確認してみましょう♪
乳幼児の医療費助成について
まずは、乳幼児の医療費助成の概要を説明します。
対象者
対象は健康保険に加入している子どもです。
給付される金額
給付される金額は、自治体によってさまざまです。
健康保険に加入している小学校就学前までの子供に対する医療費の自己負担は、全国一律2割なっています。
そこから各自治体が行う医療費助成によって、ここから自己負担額は減ります。
医療費が無料になる場合も、初診料や薬の容器代、診断書の発行などにはお金がかかる場合などもあります。
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは以下の通りです。事前に確認しておきましょう。
- 赤ちゃんを加入させた健康保険の「資格確認書」
- 申請者(生計中心者※)のマイナンバーカード
- 印鑑(必要な場合のみ)
※生計中心者とは父母のうち所得が高い人になります。
手続き時期、手続き先
手続きは、出産後、できるだけ早く行いましょう。
手続き先は住んでいる市区町村の役所の担当窓口です。
出産後すぐに病院を受診することになった場合でも助成が受けられるように、できるだけ早く申請しておくと安心です。
電子申請ができる自治体もありますのでご活用ください。
給付時期
もらえるのは年に6回、偶数月になります。
手続きをした翌月から、前月分までまとめて10日前後に振り込まれます。
手続きの流れ
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
①妊娠中
妊娠中の間に住んでいる自治体の助成内容や手続き方法を確認しておきましょう。
②出産後
出生届を提出し、赤ちゃんのマイナンバーカードが記載された住民票を取得します。
勤め先の健康保険の加入時に、赤ちゃんのマイナンバーが必要になります。
③出生届提出後
赤ちゃんを健康保険に加入させ、「資格確認書」を取得します。
勤め先の健康保険に加入している場合は職場の健康保険の窓口で、国民健康保険の場合は出生届と同日に役所で手続きをします。
④健康保険加入後
赤ちゃんの「資格確認書」を持って役所で助成の申請手続きを行います。
⑤申請後
乳幼児医療証※が発行されますので、以降の病院受診時に医療費を助成してもらえます。
※自治体によっては、乳幼児医療証を使用しないシステムになっている場合もあります。
これだけは知っておいてほしい注意点
事前にこれだけは知っておいてほしい注意点を紹介します。
住んでいる地域以外での受診時は後日払い戻しが必要
里帰りや旅行先などので、住んでいる地域以外で病院を受診する場合は、その場では医療費の助成を受けられず、医療費(2割)がかかってしまいます。
その場合、後日、住んでいる自治体に申請すれば医療費助成の対象となる費用は払い戻しが可能になりますので、領収書をなくさないように保管しておきましょう。
払い戻し方法や申請の期限などは自治体によって異なりますのでご確認ください。
手続きが遅れると医療費の立て替えが必要
乳幼児の医療費助成の手続きが完了する前に、赤ちゃんが医療機関にかかった場合は、一旦、医療費を払うことになります。
後日、払い戻しの手続きをすると助成を受けられますので、領収書を保管しておいてください。
払い戻しの手続きをなるべくしなくて済むように出産後できるだけ早く助成の手続きしましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 乳幼児医療費助成はどこまでカバーしてくれるの?
A. 一般的な診察、薬代、入院費などは対象となりますが、予防接種・健康診断・診断書発行・差額ベッド代などは対象外となることが多いです。
助成の対象範囲は自治体により異なるため、必ず公式サイトでご確認ください。
Q2. 転居した場合、医療費助成はどうなる?
A. 引越しによって自治体が変わると、新しい自治体で再度申請が必要です。
前の自治体で発行された医療証は使えなくなるため、転入届の提出後、なるべく早く新しい自治体で手続きをしましょう。
Q3. 共働き夫婦の場合、どちらが申請するの?
A. 一般的には、所得が高い方(生計中心者)が申請者となります。
ただし、扶養の関係や保険の種類によって変わる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
まとめ|赤ちゃんの医療費、助成制度を活用して安心育児を!
赤ちゃんの医療費は、回数が多い分どうしても家計の負担になりがちです。しかし、各自治体の「乳幼児医療費助成制度」を活用すれば、通院や入院の費用を大きく抑えることが可能です。
早めの申請で払い戻しの手間を減らし、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。
なお、制度の内容は変更される場合があるため、最新情報は必ずお住まいの自治体公式サイトで確認してください。
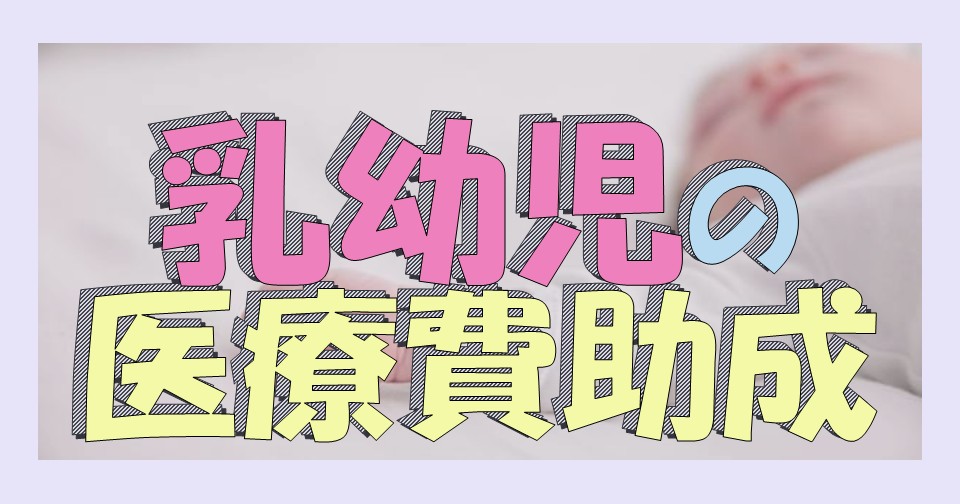
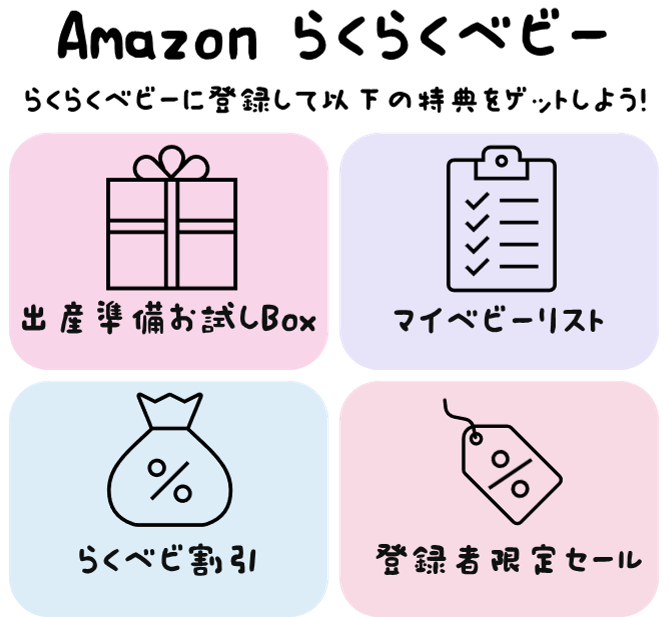
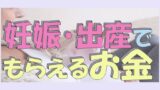

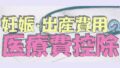

コメント